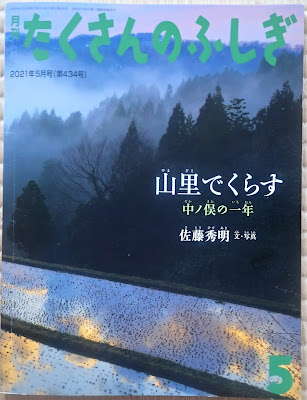昨夜、つれづれなるままにNHKのオンディマンドで、昔の映像を4Kでよみがえらせ、それに現在の映像を少し足した、「よみがえる新日本紀行『こけしの詩~宮城県鳴子町~』」を見ました。
もとの映像は、昭和46年(1971年)放送されたもの、思いがけず、冒頭からこけし工人の伊藤松三郎さんが映し出されていました。
大学1年生の夏休み、私は東北を旅したいと友人たちにもらしていました。
すると、誰かかれかが、
「あらっ、さっちゃんが東北に行きたいと言っていたよ」
「やすこさんも行きたいと言っていたよ」
と、教えてくれ、ほぼ口をきいたこともなかった同級生のさっちゃんとやすこさんと、一緒に旅することが決まりました。
当時、国鉄周遊券というものがありました。鈍行列車に限られましたが、2週間以内で、決められた区域内であれば、どこをどう乗っても、何度乗っても、料金が同じでした。私たち3人は日程を決め、コースを決めるために何度か集まりました。
私とやすこさんの行きたい場所はほんの少しで、しかも漠然としたものでした。ところが、さっちゃんには訪ねたいところがいっぱいありました。
それまで、私は郷土玩具というものの存在すら知りませんでしたが、さっちゃんは何かの会(武井武夫の会だったか?)に入っていて、あちこちの郷土玩具制作者を訪ねてみたいというのです。
結局、やすこさんと私の行きたいと思っていた、南部鉄とかホームスパンをつくっているところも計画に入れ、先生に紹介状も書いていただいたりはしましたが、全体的にはさっちゃんの行きたいところをめぐることになりました。
私たちはユースホステルの会員になって、安い宿を予約し、ユースホステルのないところでは木賃宿に泊りました。
わりと手はじめだった鳴子で、さっちゃんは町のあちこちに行きたいこけし工房があり、行く先々で、小さめのこけしをちまちまと買っていました。
こけし工人で、鳴子で一人者と言われていた伊藤松三郎さん(明治27ー昭和51年、1894ー1976年)は、温泉町ではなく、山の中に住んでいらっしゃいました。旅程も決まっていたので、松三郎さん訪問は割愛することになりましたが、せめて松三郎さんのこけしを見てみたいと訪ねたお店で、私はそのこけしに一目ぼれしてしまいました。
それまでは、伝統こけしに関心がなく、さっちゃんを覚めた目で見ていたのに、突然大きなこけしを買ってしまった私、今考えると、予算が限られていたさっちゃんはさぞ羨ましかったにちがいありません。
よく覚えていませんが、松三郎さんのこけしは1000円くらいだったかもしれません。当時は、アルバイトをすると日給で700円ほどもらえた時代、小さな土人形やコケシは、50ー200円ほどでした。
 |
| 娘さんが轆轤を回している。このあと東京に出た娘さん死亡 |
15歳で木地職人となった伊藤松三郎さんの一生は波乱万丈です。食べるために、北海道に漁業の仕事で行っては、何度も失敗に終わっています。その一生は、書き写すのさえ面倒なほど長い物語なので、Kokeshi Wikiを参照していただく以外ありません。
1971年当時、鳴子には(鳴子以外にも)蒸気機関車しか走っていませんでした。
「よみがえる新日本紀行」によると、松三郎さんは、2人の娘さんを生後1か月と、尋常小学校卒業の日に亡くされています。また、Kokeshi Wikiによると、上の写真の轆轤を手伝っていた娘さんがこのあと、東京へ出て間もなく死亡。では娘さんが3人いたのかどうかはっきりしませんが、松三郎さんが辛い人生を送っていらっしゃったことは確かです。
「よみがえる新日本紀行」には、こけしをおんぶしている子どもたちが出てきます。
こけしは本来子どものものですが、昭和40年代にはこけしの一大ブームがあったらしい、こけし愛好は子どもから、大人へと移ってはいきましたが、松三郎さんも、晩年は注文もたくさんあり、安穏に過ごせたことでしょう。
さて、我が家の松三郎こけしは、墨以外の色は褪せてしまっています。
それでも首を回すと、コリコリと、よい音がします。
まったくの余談ですが、さっちゃんには当時、スイス人のボーイフレンドがいました。招待状など、よほどのことがなければ海外に行くことのできなかった時代、さっちゃんがスイス人のボーイフレンドとつき合っているのは、海外に行く足掛かりを探しているからだと噂する人もいました。さっちゃんは、留年して1年上の学年から落ちて来た人でしたが、あまり学校には来ませんでした。
次の春休みに、また3人で一緒に、今度は関西から山陽へと旅しました。
しかし、2年生の新学期がはじまるとさっちゃんはいよいよ学校に来なくなり、その後、退学して念願通りフランスに行ったと、風の噂に聞きました。
それっきり、さっちゃんに会ったことはなく、消息も途切れたままです。
やすこさんは漆器作家として、今も活躍されています。