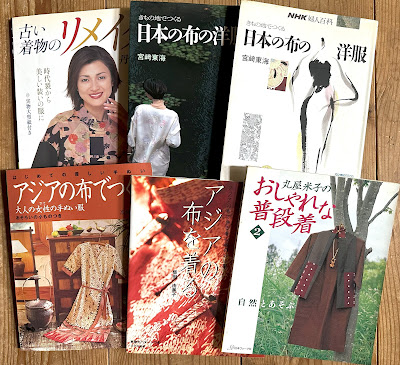長いつきあいのほん陶さんに金継ぎをお願いしていたマグカップなどが、送り返されてきました。
妹がつくったマグカップは元々6客ありました。それが4客になってしまっていたところ、縁を欠いてしまいました。どうしようか、捨ててしまおうか。マグカップに不自由しているわけではないし。と数日考えたのですが、いや待てよ、捨てるのは簡単だけど捨てたらおしまい。妹はもう焼きものをつくってないしと、なおしてもらうことにして、久しぶりにほん陶さんに連絡を取ってみました。
写真を送るときに、かねてから気になっていたキューピーのニッキ水のビンの写真も送りました。
キューピーのビンは、どうして欠けたのだったか、見るたびに心を痛めていました。以前、ほん陶さんに別のビンの接着をしてもらえないかと訊いたら、ガラスの接着はやれないとのこと、しかたなくそのビンは自分でつないだことがありました。
キューピーのビンは欠けも小さいし、ほん陶さん的には美しくないとしても、欠けっ放しよりはましだからと頼んでみたら、なんと幸運にも引き受けていただけました。
マグカップの欠けは美しくなおりました。
これでまた、活躍してくれることでしょう。
数か月前に送ったので、すっかり忘れていましたが、にゅうが入っただけのカップもなおしていただいていました。
コーヒーが染み込んだ線は汚いものですが、金継ぎの線は使うたびに楽しめます。
最高に嬉しいのはキューピーのニッキ水です。
接合したところはほとんど目立たず、欠けもあったのか、小さく金が撒かれていました。
いつもつけてくださる保証書、そして美しい字の手書きのお手紙、ほん陶さんのお人柄がしのばれます。
マグカップは空けておいた棚にぶらさげました。
金継ぎは、嬉しさを増し増しにしてくれます。